第39回日本安全保障貿易学会 研究大会終了
日本安全保障貿易学会第39回研究大会は、2025年3月16日(日)に立命館大学 大阪いばらきキャンパスにて開催された。ハイブリッド方式での開催により98名(会場52名、オンライン46名)のご参加を得て盛況であった。午前の自由論題セッションにて4件、午後のテーマセッション1、2にてそれぞれ3件の報告をいただいた。それぞれ現時点で関心の高いテーマであり、フロアからも活発な質問・意見が出された。
■自由論題セッションは5氏から4件のご報告をいただいた。
- (1) 石原 明徳氏より「1980年代に軍事運用された海外移転航空機」として、外国での軍事運用が確認された移転航空機事例について報告された。1980年代末に安全保障貿易管理制度が現在の形へと整備され、防衛装備移転政策も緩和へと向かい始めるターニングポイントとなったが、武器にあたる装備品は事実上禁輸であった。このような防衛装備移転が最厳格化していた当時にも日本から海外移転された航空機が外国で軍事運用された事例が存在したことを紹介し、防衛装備移転の対象範囲の拡大もあり得るとするとともに、維持整備体制の確立、インターオペラビリティの確保が重要であるとした。
- (2) 手塚 沙織氏より「米中関係の変容:米中間の人流データ分析から」として、米中間の人流に関するデータ分析を通じ、米国が人の国際移動の領域における対中政策において経済と安全保障のバランスをどのように変容させてきたのかが論じられた。米中間の人の移動の領域で、分野別に緩急をつけた入国/在留政策を運用した結果が見て取られ、対中に対する移民政策の運用が顕著に経済から安全保障へシフトしているとし、それを可能にした政策やその背景も合わせて議論された。
- (3) 尾崎 寛氏より「経済安全保障と金融犯罪・マネロン対策等の交錯」として、国家安全保障の観点も加え、マネロンと金融犯罪に関する対策と課題について報告された。サイバー領域における金融犯罪(特に詐欺や口座の不正利用)の脅威が世界各地で拡大している。英国では、「詐欺は国家安全保障の脅威」として官民一体で対策が進められながらも被害は拡大しており、日本でも「国民を詐欺から守る総合対策」が公表され、金融犯罪は「信頼を基礎とする社会の基盤を揺るがす脅威である」との認識が示された。FATFの第5次対日相互審査が射程に入ってきている中で、国家安全保障の観点も加えたマネロンと金融犯罪に関する対策と課題について論じられた。
- (4) 花木 正孝氏と河田 禅氏より「マネロン防止・経済安全保障対策への貿易デジタルデータ活用提言」として、新たな業界共通プラットフォーム構築について報告された。ロシアによるウクライナ侵攻を契機に、金融機関はマネロン防止・経済安全保障対策などの外国為替コンプライアンス対応の更なる強化を求められている。現在の金融機関が置かれた状況のヒアリング結果を紹介するとともに、これに対応する為の金融機関及び所管官庁、貿易プラットフォームとのデータ連携による新たな業界共通プラットフォーム設立を提言するとした。
■テーマセッション
●第1セッションでは「経済安全保障アクションプランの見直し」を取り上げた。
- (1) 西川 和見氏より「経済安全保障に関する官民連携アクション」として、経済安全保障Economic Securityに関する包括的な報告があった。90年代は自由貿易体制を指していたが、現在は国家安全保障としての経済安全保障であり、世界情勢が厳しい中でとるべき戦略の要諦は経済力と技術力を高めることにあるとした。このためにインテリジェンスを磨き、国家安全保障として関与すべき経済領域、技術領域を絞り込み、産業支援策(Promotion)、防衛策(Protection)、パートナーシップ(Partnership)の3つのPを集中させ、官民一体となって取り組むことが、日本がとるべき戦略であるとした。
- (2) 上田 広之氏より「安全保障環境の変化と対応」として、民間企業の立場から経済安全保障への取り組み状況と課題について報告があった。国際レジーム非参加の技術保有国の台頭により、同志国が連携した規制が行われてきた。さらに汎用品の軍事転用リスク増大といった情勢変化による管理対象と管理方法拡大により企業の自主管理の負荷が上がっており、高リスクの取引に適切に対処するための低リスクの取引の審査効率化など、IT化、AI活用を含めた官民の取り組みが必要であるとした。
- (3) 布施 哲氏より「経済安保におけるデータセキュリティ」として、戦略物資としてのデータについて、日米の取り組みについて報告があった。データはマイクロターゲティング技術により武器化されているとした。米国ではデータの武器化は諜報活動のみならず軍事オペレーションでも懸念されており、国家安全保障上のリスクの観点から米国司法省からデータセキュリティに関する最終規則が発行されている。日本ではデータセキュリティを経済安保でどのように規定していくか、今後の重要なテーマになるとした。
●第2セッションでは「トランプ時代の中東情勢のダイナミクス」を取り上げた。
- (1) 池内 恵氏より「中東における内生的地域秩序の形成」として、中東の地域秩序の形成について報告があった。複数の国からなるアラブは特定の支配的な国が無く、またその多くの国は体制の正当性の欠如という危機を抱えているとした。一方、イラン、イスラエル、トルコの非アラブの国の地域大国としての安定性や主権国家としての正当性は高まっており、第2次トランプ政権は、これら地域の有力国が示す秩序形成の方向性を認めていく方向にあるとした。
- (2) 坂梨 祥氏より「第2次トランプ政権とイラン・イスラエル関係」として、第2次トランプ政権の対イラン「最大限の圧力」政策による影響と、イラン・イスラエルの緊張関係の現状について報告があった。トランプ政権はイランに対し同時にディールも呼び掛けているものの、トランプ大統領が復活させた最大限の圧力政策はイランの全否定にも等しく、ディールの形が見えないとした。一方でハマスやヒズボラは壊滅状態となり安全保障上のアセットが失われた今、イラン指導部としては体制の生き残りのために国内諸派を最大限活用していくものと見られるとした。イランはその独自性を維持しつつ必要なモノは確保し続けており、その結果、輸出管理は困難なままであるとした。
- (3)江﨑 智絵氏より「イスラエルから見た中東」として、イスラエルの対外政策のひとつである周辺戦略の変容に着目したイスラエルが目指す地域秩序のあり方について報告があった。第2次トランプ政権の中東政策の一つとして、アブラハム合意の拡大がある。本報告では独立以来イスラエルがとってきた戦略と、その変容の過程が論じられ、アブラハム合意の締結およびその拡大に係るイスラエルの意図やその背景として目指されている秩序の構図について述べられた。イスラエルは2023年10月7日に発生したハマスによる襲撃事件以降の一連の紛争において勝者と言われるまでになったが、イスラエルが抱える脆弱性は本質的に変わらないのではないか、とされた。
■閉会挨拶(鈴木会長)
本日は多くの皆様にご参加いただき感謝する。安全保障貿易に関する問題は非常に幅広く、単に経済問題、貿易だけではなく、第2セッションでも見られたような中東情勢、そして第1セッションでお話のあった日本国内の経済安全保障に関する問題、自由論題でのマネーロンダリング、様々な問題が複合的に関わって、企業活動、国家安全保障、国際秩序に影響しているということを、改めて感じさせていただいた。学会の活動はこれからも重要になってくると考えており、皆様のご協力をよろしくお願いしたい。
2025年4月
日本安全保障貿易学会 会長 鈴木 一人


<会場>
日本安全保障貿易学会 第38回 研究大会プログラム
日時:2025年3月16日(日)
10:00~12:00 自由論題セッション
13:00~14:50 第1セッション
15:00~16:50 第2セッション
会場: 立命館大学(大阪/茨木市) 大阪いばらきキャンパス C棟
大阪府茨木市岩倉町2-150
■自由論題セッション 10:00~12:00
(1)石原 明徳氏(防衛研究所・立命館大学)
「1980年代に軍事運用された海外移転航空機- 過去事例が語る防衛装備移転への歴史的示唆」
(2)手塚 沙織氏(南山大学)
「米中関係の変容:米中間の人流データ分析から」
(3)尾崎 寛氏(KPMGあずさ監査法人)
「経済安全保障と金融犯罪・マネロン対策等の交錯」
(4)花木 正孝氏/河田 禅氏(近畿大学/NTTデータ)
「マネロン防止・経済安全保障対策への貿易デジタルデータ活用提言-新たな業界共通プラットフォーム構築」
司会討論者:高野 順一氏(日本輸出管理研究所(学会副会長))
■テーマセッション
●第1セッション <経済安全保障アクションプランの見直し> 13:00~14:50
(1)西川 和見氏(経済産業省)
「経済安全保障に関する官民連携アクション」
(2)上田 広之氏(三菱電機)
「安全保障環境の変化と対応」
(3)布施 哲氏(IISE特別研究主幹、信州大学特任教授)
「経済安保におけるデータセキュリティ 基本的論点の整理」
司会討論者:小野 純子氏(外務省(学会理事))
●第2セッション <トランプ時代の中東情勢のダイナミクス> 15:00~16:50
(1)池内 恵氏(東京大学)
「中東における内生的地域秩序の形成 シリア内戦終結過程を題材に」
(2)坂梨 祥氏(日本エネルギー経済研究所)
「第2次トランプ政権とイラン・イスラエル関係」
(3)江﨑 智絵氏(防衛大学校)
「イスラエルから見た中東 ―周辺戦略の変容に着目して」
司会討論者:鈴木 一人氏(東京大学(学会会長))
■自由論題セッション

石原 明徳氏 「1980年代に軍事運用された海外移転航空機 - 過去事例が語る防衛装備移転への歴史的示唆」
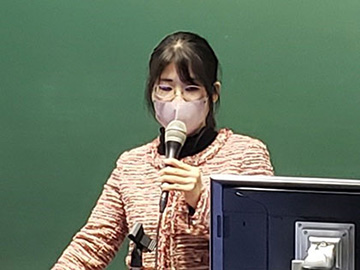
手塚 沙織氏 「米中関係の変容: 米中間の人流データ分析から」

尾崎 寛氏 「経済安全保障と金融犯罪・マネロン対策等の交錯」


花木 正孝氏/河田 禅氏「マネロン防止・経済安全保障対策への貿易デジタルデータ活用提言-新たな業界共通プラットフォーム構築」

司会討論者:高野 順一氏
■テーマセッション
●第1セッション <経済安全保障アクションプランの見直し>
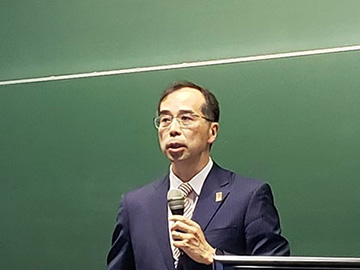
西川 和見氏 「経済安全保障に関する官民連携アクション」
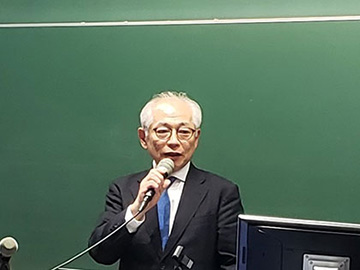
上田 広之氏 「安全保障環境の変化と対応」

布施 哲氏 「経済安保におけるデータセキュリティ基本的論点の整理」
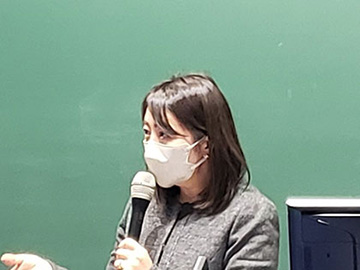
司会討論者:小野 純子氏
■テーマセッション
●第2セッション <トランプ時代の中東情勢のダイナミクス>
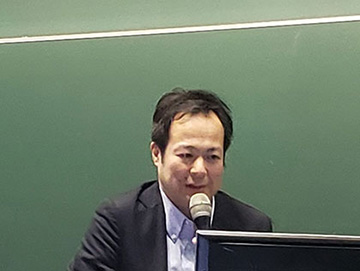
池内 恵氏 「中東における内生的地域秩序の形成 シリア内戦終結過程を題材に」
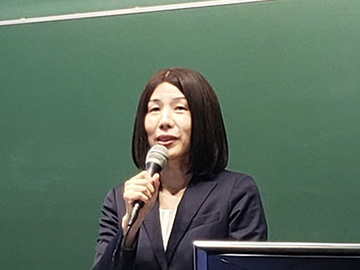
坂梨 祥氏 「第2次トランプ政権とイラン・イスラエル関係」
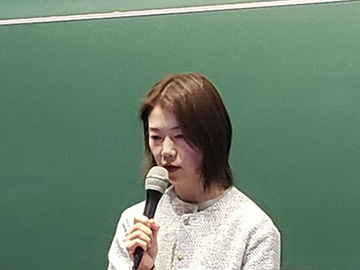
江﨑 智絵氏 「イスラエルから見た中東
―周辺戦略の変容に着目して」
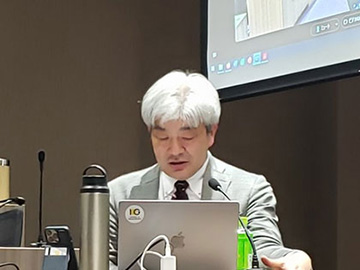
司会討論者: 鈴木 一人氏
